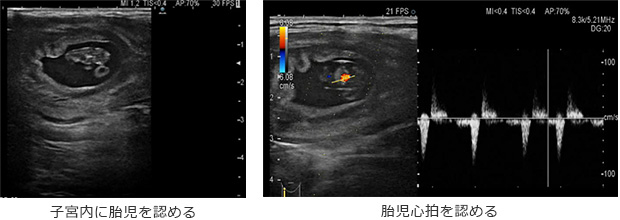北澤晶子君(95期)が第136回関東連合産科婦人科学会総会・学術集会で優秀演題賞を受賞
 平成30年11月24日、25日に一橋大学一橋講堂で開催された第136回関東連合産科婦人科学会総会・学術集会において、教室の北澤晶子君(95期)が優秀演題賞を受賞した。同君の演題は「若年子宮体癌/子宮内膜異型増殖症に対する高用量黄体ホルモン療法の再発例の検討」であり、近年増加傾向にある若年性子宮体癌における妊孕性温存療法についての発表である。2018年に子宮体がん治療ガイドラインが改訂され、再発例に対しても黄体ホルモン療法を行うことを許容する内容に変更となったが、その妥当性やエビデンスの蓄積は十分とはいえないが現状であった。本発表は当院で高用量黄体ホルモン療法を施行した患者を後方視的に検討し、再発例を詳細に検討した。再発に影響を与える因子として組織型、妊娠の有無が重要であることを確認し、再発例の治療効果に影響を与える因子として初回治療前の組織型が重要であり、一度再発した場合、妊娠の有無は治療効果には影響しないことを示した。再発例を詳細に検討した報告例は乏しく、再発症例に妊孕性温存療法を行う上で非常に有用なデータである。182症例における膨大なデータを、緻密にかつわかりやすくまとめ、煩雑になりがちなプレゼンテーションを明快に示すことができたことが高く評価され今回の受賞に至った。同君は現在後期研修1年目であるが、忙しい日常診療の傍らデータをまとめ発表準備をし、今回の受賞に至った。今回の経験をいかして出張先でも研鑽を積み、さらなる飛躍を期待したい。
平成30年11月24日、25日に一橋大学一橋講堂で開催された第136回関東連合産科婦人科学会総会・学術集会において、教室の北澤晶子君(95期)が優秀演題賞を受賞した。同君の演題は「若年子宮体癌/子宮内膜異型増殖症に対する高用量黄体ホルモン療法の再発例の検討」であり、近年増加傾向にある若年性子宮体癌における妊孕性温存療法についての発表である。2018年に子宮体がん治療ガイドラインが改訂され、再発例に対しても黄体ホルモン療法を行うことを許容する内容に変更となったが、その妥当性やエビデンスの蓄積は十分とはいえないが現状であった。本発表は当院で高用量黄体ホルモン療法を施行した患者を後方視的に検討し、再発例を詳細に検討した。再発に影響を与える因子として組織型、妊娠の有無が重要であることを確認し、再発例の治療効果に影響を与える因子として初回治療前の組織型が重要であり、一度再発した場合、妊娠の有無は治療効果には影響しないことを示した。再発例を詳細に検討した報告例は乏しく、再発症例に妊孕性温存療法を行う上で非常に有用なデータである。182症例における膨大なデータを、緻密にかつわかりやすくまとめ、煩雑になりがちなプレゼンテーションを明快に示すことができたことが高く評価され今回の受賞に至った。同君は現在後期研修1年目であるが、忙しい日常診療の傍らデータをまとめ発表準備をし、今回の受賞に至った。今回の経験をいかして出張先でも研鑽を積み、さらなる飛躍を期待したい。
(88期 真壁 健 記)
 升田君は平成30年7月26日から27日に千葉県の幕張メッセにて行われた第36回日本受精着床学会総会・学術講演会において、「子宮内膜症と上皮間葉転換の関連の解明および上皮間葉転換阻害薬のもつ新規子宮内膜症治療薬としての可能性の検討」という演題で発表し、世界体外受精会議記念賞を受賞した。日本受精着床学会は、当教室の教授であった飯塚理八先生が発起人代表として1982年に発足した、生殖補助医療の向上を目的とした学会である。不妊治療に携わる産婦人科医、泌尿器科医、胚培養士および生殖生物学の研究者を中心としたとした学会であり、総会・学術講演会への参加者は今回、1,400人を超えた。本賞はかつてこの学会が世界体外受精会議を同時主催した際に設立された記念基金によって、本邦の生殖医学・医療の発展に寄与しうる優れた学術集会報告を表彰するために設けられた比較的歴史の長い賞である。
升田君は平成30年7月26日から27日に千葉県の幕張メッセにて行われた第36回日本受精着床学会総会・学術講演会において、「子宮内膜症と上皮間葉転換の関連の解明および上皮間葉転換阻害薬のもつ新規子宮内膜症治療薬としての可能性の検討」という演題で発表し、世界体外受精会議記念賞を受賞した。日本受精着床学会は、当教室の教授であった飯塚理八先生が発起人代表として1982年に発足した、生殖補助医療の向上を目的とした学会である。不妊治療に携わる産婦人科医、泌尿器科医、胚培養士および生殖生物学の研究者を中心としたとした学会であり、総会・学術講演会への参加者は今回、1,400人を超えた。本賞はかつてこの学会が世界体外受精会議を同時主催した際に設立された記念基金によって、本邦の生殖医学・医療の発展に寄与しうる優れた学術集会報告を表彰するために設けられた比較的歴史の長い賞である。 平成30年5月10日から13日にかけて仙台で開催された第70回日本産科婦人科学会学術講演会にて、村上 功君(82期)がJSOG Congress Encouragement Awardを受賞した。同賞はレフリーの評価が高い演題で構成されるInternational Workshop演題の中から、発表における評価が特に高い演者に授与される賞である。
平成30年5月10日から13日にかけて仙台で開催された第70回日本産科婦人科学会学術講演会にて、村上 功君(82期)がJSOG Congress Encouragement Awardを受賞した。同賞はレフリーの評価が高い演題で構成されるInternational Workshop演題の中から、発表における評価が特に高い演者に授与される賞である。 平成30年5月10日から13日に仙台市で開催された第70回日本産科婦人科学会学術講演会において木須伊織君が優秀日本語演題賞を受賞した。
平成30年5月10日から13日に仙台市で開催された第70回日本産科婦人科学会学術講演会において木須伊織君が優秀日本語演題賞を受賞した。 同君は子宮移植の臨床応用を目指すため、非ヒト霊長類動物であるカニクイザルを用いて子宮移植実験を行ってきた。慶應大学医学部キャンパス内ではカニクイザルの飼育、手術や管理は行えないため、滋賀医科大学の動物実験センターまで幾度も足を運び、実験をこれまで継続的に行うことができているのは同君の努力の結晶ともいえる。また、カニクイザルを用いた侵襲の高い複雑な手術、術中術後管理、免疫抑制剤のコントロールなどはヒトと異なり、非常に困難を極める。それにも関わらず、同君はそれらの課題を一つずつ解決しながら、これまで本研究を飛躍的に進め、今回の受賞は同君のこれまでの苦労や多くの業績が高く評価された。また、これまで慶應外科の先生方を中心に多岐に渡る領域の先生方と協力しながら研究を進めており、日本チームの基礎実験の業績は国際的に最も高く評価されている。
同君は子宮移植の臨床応用を目指すため、非ヒト霊長類動物であるカニクイザルを用いて子宮移植実験を行ってきた。慶應大学医学部キャンパス内ではカニクイザルの飼育、手術や管理は行えないため、滋賀医科大学の動物実験センターまで幾度も足を運び、実験をこれまで継続的に行うことができているのは同君の努力の結晶ともいえる。また、カニクイザルを用いた侵襲の高い複雑な手術、術中術後管理、免疫抑制剤のコントロールなどはヒトと異なり、非常に困難を極める。それにも関わらず、同君はそれらの課題を一つずつ解決しながら、これまで本研究を飛躍的に進め、今回の受賞は同君のこれまでの苦労や多くの業績が高く評価された。また、これまで慶應外科の先生方を中心に多岐に渡る領域の先生方と協力しながら研究を進めており、日本チームの基礎実験の業績は国際的に最も高く評価されている。